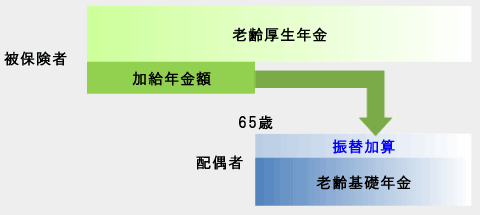老齢厚生年金
- ※ 平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」についての説明です。
- ※ 同年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」については、こちらのページをご参照ください。
1 受給資格
老齢厚生年金は、65歳から支給され、受給資格は次のアからウまでのすべての要件に該当したときとなっています。
- ア 65歳以上であること
- イ 1か月以上の被保険者期間を有すること
- ウ 保険料納付済期間と保険料免除期間(※1)を合算した期間が10年以上(※2)であること
※1 保険料納付済期間とは、国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員であった期間をいい、保険料免除期間とは、国民年金の保険料免除期間をいいます。
※2 平成29年8月1日施行の法律改正により、受給資格期間が「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。
2 老齢厚生年金の額
(1)老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の額は、次のように計算します。
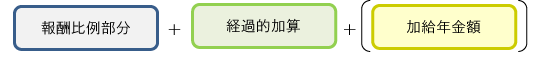
この他、平成27年9月までの公務員共済組合の加入期間をもとに、旧退職共済年金における職域年金相当部分に該当する経過的職域加算額(退職共済年金)を、平成27年10月以降の公務員期間を基礎とする、公的年金とは別枠の年金払い退職給付を、それぞれお支払いします。
(2)報酬比例部分
報酬比例部分の計算式については、次のとおりです。
-
(平成15年3月31日までの期間) 平均標準報酬月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの被保険者(組合員)期間の月数 +
(平成15年4月1日以後の期間) 平均標準報酬額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の被保険者(組合員)期間の月数
- ※1 複数の厚生年金の被保険者期間をお持ちの方は、それぞれの年金保険者が老齢厚生年金をお支払いします。詳しくは、概要のページをご覧ください。
- ※2 被用者年金が一元化された平成27年10月前の地方公務員共済組合の組合員期間は、そのまま厚生年金保険の被保険者期間とみなされます。
(3)経過的加算
被保険者期間のうち、国民年金の老齢基礎年金の算定の基礎とならない期間(20歳前及び60歳以後の期間等)にかかる加算です。
経過的加算の計算式については、次のとおりです。
-
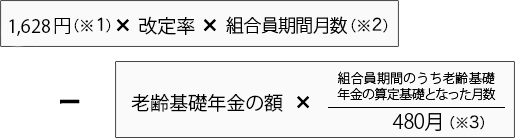
令和7年度の改定率
- 昭和31年4月1日以前生まれの方…1.062
- 昭和31年4月2日以降生まれの方…1.065
(※1) 昭和21年4月1日以前の生まれの方は年齢に応じた率を乗じます。
(※2) 昭和21年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。なお、昭和21年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて上限月数が決まっています。
(※3) 昭和16年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。なお、昭和16年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて上限月数が決まっています。
基礎年金関係
- 65歳以上の方は、老齢基礎年金が国民年金制度から別に支給されます。
老齢基礎年金
- 国民年金制度の老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間、国民年金制度に加入していた場合(厚生年金の被保険者期間及び共済組合の組合員であった期間で20歳から60歳までの期間も、国民年金制度に加入していた期間とみなされます。)、満額となります。ただし、この「40年間」という期間を満たすことができない方については次のとおりその加入していた期間に応じた金額になります。
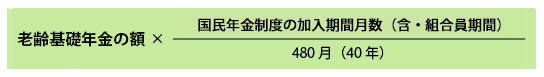
(4)加給年金額
老齢厚生年金の受給者で、被保険者期間(公務員の期間と民間等にお勤めの期間を合算した期間)が20年以上ある方が65歳になられた当時、老齢厚生年金の受給者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障がいの状態である未婚の子がいるときは、加給年金額が加算されます。
加給年金の金額(令和7年度の額)
| 受給者の生年月日 | 加給年金額 |
|---|---|
| 昭和18年4月2日~ | 415,900円 |
| 子の人数 | 加給年金額 |
|---|---|
| 2人目まで1人につき | 239,300円 |
| 3人目から1人につき | 79,800円 |
ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。
○ 加入期間が20年以上である老齢厚生年金
※ 国民年金制度の老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
○ 障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等
(基礎年金関係)振替加算
加給年金額対象者となっていた配偶者が65歳になると、加給年金額は加算されなくなりますが、代わりに配偶者(昭和41年4月1日までに生まれた方に限る。)の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
ただし、加給年金額対象者が、加入期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権があるときは、振替加算は加算されません。
振替加算の額は、生年月日(=老齢基礎年金加入可能期間)に応じ、異なります。
※ 加給年金額対象者とならない方でも、一定の要件を満たしていれば振替加算が加算される場合があります。
(5)老齢厚生年金の支給の繰上げ
昭和36年4月2日以降に生まれた方の老齢厚生年金は、後述の「3 特別支給の老齢厚生年金」が支給されずに65歳からの支給となりますが、60歳到達後は、希望により繰り上げて受給することができます。
この繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、繰上げ請求をした月からその方が65歳に達する月の前月までの月数について、1か月あたり0.4%(1年あたり4.8%)減額(※)されます。
なお、繰上げ支給にかかる注意事項については、後述の「3 特別支給の老齢厚生年金」の「(5)特別支給の老齢厚生年金の支給の繰上げ」でご確認ください。
※昭和37年4月1日以前に生まれた方及び令和4年3月31日までに繰上げ請求をした場合、1か月あたり0.5%(1年あたり6%)が減額されます。
(6)老齢厚生年金の支給の繰下げ
老齢厚生年金は、支給繰下げの制度があります。
これは、希望により、老齢厚生年金を66歳以降から繰り下げて受給することにより、繰り下げる月数に応じて計算した加算額を本来の年金額に加算して受給することができるものです(注)。
(注)65歳から受給開始までの間は支給がありません。なお、複数の老齢厚生年金の受給権をお持ちの場合は、一部のみ繰り下げることは認められません。たとえば、民間会社分と公務員期間分の両方の老齢厚生年金の受給権をお持ちの場合は、同時に繰下げをしなければなりません。
ただし、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に支給繰下げを希望する必要はありません。
1ヶ月あたり0.7%(年率8.4%)の加算額(120月限度※)になりますが、厚生年金保険の被保険者等であることによる年金の停止など、年金額に停止額がある場合は、実際に支給を受けられる額に対して加算額を計算することとなります。
(支給の繰下げができない場合)
老齢厚生年金以外に他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権もあわせてお持ちであれば、希望があっても、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできません。また、繰下げを予定されていた方で、66歳に到達した後に他の公的年金の受給権者となった方は、その受給権者となった日まで繰り下げた老齢厚生年金を請求するか、繰下げをしない65歳からの老齢厚生年金を請求することになります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方及び令和4年3月31日までに繰下げの請求をされている場合は60月限度
令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ、65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、以下のとおりとなります。
- ・老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求をすることができるようになります。
- ・老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求をすることができるようになります。
3 特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金は、本来65歳から支給されることとされていますが、従来60歳から年金が支給されていたことから、当面の間、経過措置として65歳未満であっても特別支給の老齢厚生年金が支給されることとされています。
(1)受給資格
特別支給の老齢厚生年金の受給資格は、次のアからウまでのすべての要件に該当したときです。
-
- ア 60歳以上65歳未満であること
- イ 1年以上の被保険者期間(公務員である被保険者期間と民間の被保険者期間を合算した期間です)を有すること
- ウ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であること
(2)支給開始年齢の引き上げ
昭和28年4月2日以降に生まれた方については、以下のとおり、支給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金は発生しません。
なお、民間企業期間の特別支給の老齢厚生年金は、女性の場合は下記の表から6年遅れで支給開始年齢が引き上げられることとなっています。しかし、公務員期間の特別支給の老齢厚生年金は、女性であっても男性と同様の支給開始年齢となっています。
| 生年月日 | 支給開始年齢 |
|---|---|
| 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
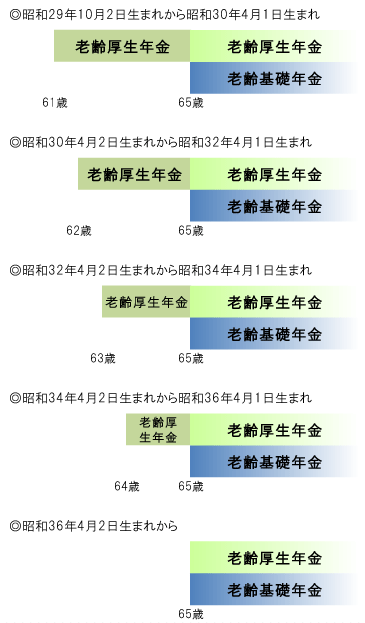
※ 昭和29年10月1日以前の生まれの方は、平成27年10月1日の被用者年金一元化前に支給開始年齢に到達するため、共済組合に加入していた期間について65歳までの間に受給される年金は退職共済年金となります。退職共済年金については、こちらをご覧ください。
(3)特別支給の老齢厚生年金の額(65歳未満の方が受給)
特別支給の老齢厚生年金の額は、次のように計算します。
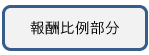
報酬比例部分(厚生年金相当部分)
-
(平成15年3月31日までの期間) 平均標準報酬月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの被保険者(組合員)期間の月数 +
(平成15年4月1日以後の期間) 平均標準報酬額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の被保険者(組合員)期間
※1 加給年金額は、定額部分の支給がある方については、定額部分と同時に給付されていましたが、特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分のみとなる方(原則として昭和24年4月2日以降に生まれた方)は、65歳から支給される本来支給の年金に加算されます。
※2 障がい者の方及び長期在職者の方は、給付の特例がありますので、下記(4)を参照してください。
(4)障がい者の方及び長期在職者の方の特例
特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳に達するまでに被保険者の資格を喪失し、障害等級1級から3級の障がいの状態にあり、かつ、障害者特例の請求を行った場合、または、公務員共済組合の期間である厚生年金被保険者期間が44年以上である場合は、定額部分が加算されます。また、該当者の被保険者期間(公務員期間と民間企業等にお勤めの期間を合算した期間)が20年以上である場合は、加給年金額が加算されます(加給年金額は要件に該当する場合に加算されます。)。
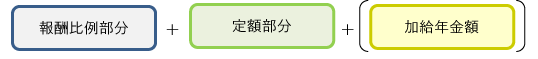
定額部分
定額部分の計算式については、次のとおりです。
| 1,628円 × 改定率 × 組合員期間の月数(※1) |
|---|
定額部分とは、老齢基礎年金に相当する額です。
令和7年度の改定率…1.065
(※1) 昭和21年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。なお、昭和21年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて上限月数が決まっています。
(5)特別支給の老齢厚生年金の支給の繰上げ
昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた方については、60歳到達後は、希望により、特別支給の老齢厚生年金を支給開始年齢前から繰り上げて早めに受給することができます。
この繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、繰上げ請求をした月からその方の生年月日に応じた支給開始年齢に達する月の前月までの月数について、1ヶ月当たり0.5%(1年あたり6%)減額されます。
繰上げ支給の老齢厚生年金は、次のような制約等がありますので、繰上げ請求に当たってはその制約等を理解していただき、その請求は慎重にお願いします。
注意事項
- 繰上げ請求後はその決定を取消すことはできず、終生減額された年金額となります。
- 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害厚生年金(障害基礎年金、公務員期間以外の期間で発生した障害厚生年金を含む)を請求することはできません。
- 繰上げ請求する場合は、受給資格を有する他の年金(老齢基礎年金、公務員期間以外に期間で発生した老齢厚生年金等を含む)の繰上げ請求を同時に行わなければなりません。
- 繰上げ請求後は、国民年金に任意加入できません。
- 繰上げ請求後は、原則、老齢厚生年金の障がいの特例や長期在職者の特例に該当しても、これらの適用は受けることができません。
- ※ 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳です。60歳から繰上げを受けると、24%(0.4%×12月×5年)減額となりますので、ご留意ください。
4 公務員在職中に老齢厚生年金が決定及び改定(在職定時改定)され、その後退職したとき(退職改定)
公務員として在職中に決定された老齢厚生年金は、在職している間は下記5の在職老齢年金に該当し、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。その後、退職したときには、在職中に決定及び改定された老齢厚生年金の算定基礎となった被保険者期間に、退職までの被保険者期間を加えるとともに、平均標準報酬額の見直しを行い、年金額を改定します。
- ※ 退職までの被保険者期間を加えて改定した結果は、「年金額改定・支給額変更通知書」によりお知らせいたします。
なお、65歳以上70歳未満の被保険者の方については、毎年1回10月に年金額の改定を行います(在職定時改定)。
- ※ 65歳未満の方は、繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象とはなりません。
5 再就職した場合等の老齢厚生年金(在職老齢年金)
働きながら年金を受給する方のうち、給与と年金を合わせて一定額を超える場合は、年金額を調整することとなっています。
年金受給権者が厚生年金の被保険者等である間は、その方の総報酬月額相当額(標準報酬月額と、過去1年間の標準賞与額×1/12の合算額)と基本月額(老齢厚生年金のうち加給年金額及び経過的加算額を除いた額との合算額)との合計額に応じて、年金の一部が支給停止されます。
ア 厚生年金保険の被保険者等とは
- ○ 厚生年金保険の被保険者(民間企業や公務員等を問わず、すべて含まれます)
- ○ 70歳以上で厚生年金の適用事業所に常時勤務する方
- ○ 国会議員または地方議会の議員
イ 標準報酬月額等及び標準賞与額等とは
- ○ 厚生年金保険の被保険者または70歳以上の被用者の場合は、標準報酬月額及び標準賞与額をいいます。
- ○ 国会議員または地方議会議員の場合は、歳費月額(または議員報酬月額)及び期末手当の額をいいます。
在職老齢年金の計算方法
-
→ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が51万円を上回る分の半分が停止されます。
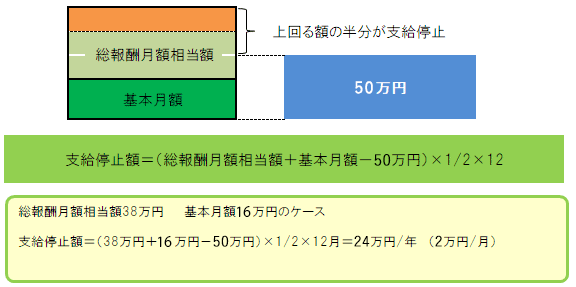
- ※1 加給年金額が決定されている方は、別途加給年金額が加算されます。ただし、支給停止額の計算の結果、全額停止となる場合は支給されません。
6 雇用保険法による給付との調整
(1)基本手当(失業給付)との調整
65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、一定の間、老齢厚生年金の全額が停止されます。
失業給付の額が年金額を下回っていた場合でも差額は受けられません。ハローワークで求職の申込みをする前に、基本手当の額を試算し、老齢厚生年金の額と比較のうえ、有利な方を選択するようにしてください。
(2)高年齢雇用継続給付との調整
65歳になるまでの老齢厚生年金の受給者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けており、前記5の在職老齢年金を受けている場合は、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が停止される場合があります。
なお、停止額は最高で標準報酬月額の6%相当額となります。
公務員共済組合期間に係る老齢厚生年金のほか、日本年金機構からの老齢厚生年金を受けている場合は、停止額に老齢厚生年金の合計額に対するそれぞれの額の占める割合を乗じて得た額をそれぞれ停止されることとなります。
7 退職一時金の返還
過去の年金制度に基づき退職一時金の支給を受けた方が、老齢厚生年金を受給する権利を取得したときは、その退職一時金の額に利子に相当する額を加え、老齢厚生年金を受給する権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時にまたは分割して返還しなければならないこととされています。
また、老齢厚生年金の請求時に年金からの控除を申し出た方につきましては、上記にかかわらず、老齢厚生年金の支給期ごとの支給額の2分の1に相当する金額を返還すべき金額に達するまで順次控除することとされています。
8 老齢厚生年金の受給権の消滅
老齢厚生年金の受給権者が亡くなられたときは、その権利が消滅します。
なお、亡くなられた当時、亡くなられた方に生計を維持されていた方で一定の要件に該当する方がいらっしゃる場合は、その方に遺族厚生年金が支給されます。